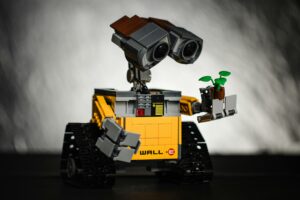1. はじめに
現代社会の急速な技術進歩により、電子部品の高性能化と小型化が同時に進行している12。この技術トレンドは、半導体デバイスの発熱密度を飛躍的に増加させ、従来の冷却手法では対応困難な熱問題を引き起こしている34。特に人工知能(AI)技術の普及により、データセンターやエッジコンピューティング環境における高性能プロセッサの発熱量は従来比で数十倍に達し、冷却能力の不足が機器の性能制限や寿命短縮の原因となっている56。
近年のテクニカルタームを解説すると、「発熱密度」とは単位面積当たりの熱発生量を指し、AIサーバーでは将来的に100W/cm²を超える予測がされている3。「熱流束」は単位時間に単位面積を通過する熱量で、冷却システムの性能指標として用いられる。また「二相冷却」とは液体の蒸発と凝縮を利用した冷却方式で、液体の気化熱により高い冷却効率を実現する技術である27。
電子機器における熱設計の根本的な目的は、半導体素子や内部デバイスを許容温度内に抑え、装置の正常動作と長期信頼性を保証することである1。しかし、情報通信機器では処理熱量増大の一方で対策スペースが減少し、内部熱現象が複雑化している1。3次元CADによる高密度実装設計技術の進歩は、筐体内の空隙率低下を招き、冷却デバイスの設置スペースと冷却流路を減少させている1。
本レポートは、このような背景を踏まえ、冷却システムの現状と課題を分析し、次世代技術の動向と将来展望を包括的に検討することを目的とする。
※本ページは、AIの活用や研究に関連する原理・機器・デバイスについて学ぶために、個人的に整理・記述しているものです。内容には誤りや見落としが含まれている可能性もありますので、もしお気づきの点やご助言等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
※本ページの内容は、個人的な学習および情報整理を目的として提供しているものであり、その正確性、完全性、有用性等についていかなる保証も行いません。本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことによって発生した損害(直接的・間接的・特別・偶発的・結果的損害を含みますが、これらに限りません)について、当方は一切責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の責任でお願いいたします。
2. 電子部品冷却の現状と課題
2.1 現在主流の冷却方式
現在の電子機器冷却では、主に空冷、液冷、ヒートシンクを中心とした複数の方式が使い分けられている89。
空冷方式は最も一般的な冷却手法で、自然対流を利用する自然空冷方式とファンによる強制対流を用いる強制空冷方式に分類される8。自然空冷式は保守性に優れ製造コストが低い利点がある一方、放熱性能が限定的で高発熱デバイスへの対応が困難である8。強制空冷による冷却性能は1ラックあたり10kW程度とされ、一般的なCPUサーバー(220W程度)には十分対応可能である10。
液冷方式は空気の100倍という優れた熱輸送効率を持つ冷媒を利用する11。不凍液などの液体による冷却方式では、液冷や強制空冷方式を採用したヒートシンクの方が自然空冷方式より放熱性に優れている8。しかし生産コストが高く、ポンプやファンによる騒音、長期使用時の信頼性低下などの問題がある8。
ヒートシンク技術では、アルミニウムや銅材料を用いたフィン構造により表面積を拡大し、熱放散を促進する8。製造方法としてはカシメ、ブレージング(ろう付け)、鍛造、押出し等があり、複雑な3次元形状は高価である一方、押出し材は安価で大量製造が可能である8。
2.2 現行システムの限界と課題
空冷システムの物理的限界として、研究報告によると空冷2Uサーバースペースでは約250W、4Uスペースでは400W~600Wが冷却能力の上限とされている6。これに対し、NVIDIA H100チップのような高性能AIプロセッサでは4Uラックが必要となり、スペース効率の問題が顕在化している6。
従来の空冷方式では、熱を逃がすためにラックの容量より間引いてサーバを搭載する「間引き搭載」が必要で、スペースの無駄遣いが発生している12。また空気は断熱材として使われることからも理解できるように、熱を運ぶ媒体としての効率は良くない11。
エネルギー消費の課題として、データセンター関連の電気代の30%は機器を冷やすためのファンに使われており5、冷却負荷だけでデータセンターのエネルギー消費の最大40%を占めている13。2030年までにデータセンターは冷却だけで900TWhのエネルギーを消費すると予測されている13。
騒音問題も深刻で、空調設備のファンが回る音は予想以上に大きく12、データセンター運営において環境課題となっている。冷却ファンやパワーコンディショナが発する騒音は、特に夜間や静寂な環境で目立ち、周辺住民からの苦情原因となるケースも報告されている14。
3. 次世代冷却材料の開発動向
3.1 グラフェンの応用可能性
グラフェンは炭素原子が六角形格子構造を成す二次元原子結晶で、室温においてダイヤモンドと同程度の熱伝導率(~数千W/(m·K))を持つことが報告されている1516。グラフェンは強度が高く軽量でありながら非常に柔軟で、極めて優れた機械的剛性、高い弾性、優れた電気伝導性と熱伝導性を示す16。
具体的な応用例として、発熱部と放熱部をグラフェンで接続する研究や、フィラー材として除熱機構への応用を目指す研究が行われている15。大阪ガスグループは低コストで分散性の高い多層グラフェンを開発し、高い熱伝導率と輻射率の相乗効果で熱を素早く拡散し、系外に放出する特性を確認している17。
しかし、グラフェンの熱伝導率は構造中の欠陥や不純物の存在により大幅に低下するため15、実用化においては製造品質の管理が重要な課題となっている。
3.2 カーボンナノチューブの特性と課題
カーボンナノチューブ(CNT)は本質的にグラフェンシートを丸めた構造で、室温でダイヤモンド並みの熱伝導率を持つ1518。CNTとグラフェンが高い熱伝導性を持つ理由は、熱キャリアであるフォノンの効率的な伝達にある15。
CNTの熱伝導特性に関する課題として、材料の大きさによってフォノンの自由行程が制限され、熱伝導率が変化することが挙げられる15。また、欠陥や不純物が少量でも存在するとフォノンが散乱され、熱伝導率が低下する問題がある15。
実用化に向けた研究として、垂直配向カーボンナノチューブとパリレンによる高熱伝導性複合材料の開発が進められており、加熱浸透法によるパリレンの浸透率向上や、フォトサーマル赤外検知法による熱伝導率評価の研究が行われている19。
3.3 合成ダイヤモンドの熱管理応用
合成ダイヤモンドは銅と比べて熱伝導率が2000W/mK以上と、銅の5倍以上の優れた熱伝導性を持つ2021。Element Six社は薄膜の合成ダイヤモンドを製造し、エレクトロニクス分野への応用を進めている20。
ダイヤモンドヒートスプレッダーの特徴として、最高の熱伝導率(約1,500~2,200 W/mK)と最高の電気絶縁体という2つの重要な特性を併せ持つ21。これにより、可能な限り高い熱流量と電気的絶縁が必要な用途に最適である21。
その他の利点として、軽量性、熱安定性(小さい熱膨張係数)、耐食性、卓越した硬さ、光透過性などがある21。応用分野として、衛星通信用高出力RFデバイス、高出力レーザー半導体、レーザー鏡、ディスクレーザーなどに使用されている21。
製造技術として、化学蒸着(CVD)加工方法でダイヤモンドを製造し、特殊な高温チャンバー内でメタンガスにマイクロ波を照射してプラズマを発生させ、遊離炭素原子をダイヤモンドシード層に堆積させる21。現在5インチウェーハでの合成を主力製品とし、最大直径138mmの基板まで製造可能である20。
4. 新しい冷却技術の進展
4.1 フェーズチェンジマテリアル(PCM)
フェーズチェンジマテリアル(PCM)は、温度変化に伴って固体と液体の相変化を行うことで大量のエネルギーを吸収または放出する材料である2223。この特性を利用して温度管理やエネルギー効率の向上に使用され、建築物の温度調整、医療用途、食品輸送、エレクトロニクスの冷却などに応用されている22。
PCMの動作原理として、熱により軟化して密着性が向上することで優れた放熱性能を発揮する23。信越シリコーンのシリコーンPCMは、圧縮後の厚みが非常に薄く(圧縮後の最薄厚み:10μm)、耐ポンプアウト性に優れている2324。
技術的特徴として、非シリコーンのフェーズチェンジ製品では実現困難な高温領域での長期信頼性を実現している23。熱設計電力(TDP)の制限があり、単相浸漬冷却ではGPUのTDPが700ワットを超えると効果的な冷却が困難になる可能性がある25。
4.2 マイクロ流体冷却技術
マイクロチャネル冷却は微細加工技術を使って加工した狭隘な流路を利用した技術で、一般的に熱交換器の管内熱伝達率は管の流路断面寸法の逆数に比例して向上する26。
東京大学生産技術研究所の野村政宏教授らが開発した三次元マイクロ流路システムは、世界最高レベルの冷却効率を実現している24。この技術の特徴として、「マニホールド構造」と「キャピラリー構造」を組み合わせることで、従来の冷却方法と比べて圧力損失を62%削減しながら、1cm²あたり700W以上の放熱能力を実証している2。
技術的仕組みとして、冷却水はマニホールド構造で効率よく分配され、マイクロ流路の側壁付近に設置された微細なマイクロピラーがキャピラリー構造として機能し、毛細管現象により水の薄い膜が熱いシリコンに接触しやすくなる24。
4.3 二相冷却システム
二相冷却技術は液体の蒸発と凝縮のサイクルを利用した高効率冷却システムで、単相式と二相式に分類される2527。
単相式液浸冷却では、すべてのサーバーとIT機器を絶縁液体に完全に浸漬し、CPUやGPUなどのコンポーネントの温度上昇により液体が熱を吸収し、加熱された液体は熱交換ユニットで冷却される25。
二相式液浸冷却では、機器が加熱されると液体が沸騰して蒸気が発生し、蒸気は液体タンクの上部で冷却パイプと接触して凝縮し、再び液体となってタンクに滴り落ちる25。Opteon™ 2P50誘電性流体を使用した二相式液浸冷却では、データセンターの冷却エネルギーを90%以上削減可能とされている27。
山口東京理科大学の革新技術として、人の呼吸現象を応用した「ブリージング現象」を利用した二相液浸冷却技術が開発され、従来の実装可能な二相液浸技術の最大性能300W/cm²に対し、未踏の735W/cm²を達成している283。
5. AI・機械学習による冷却最適化
5.1 リアルタイム温度管理システム
Googleの先駆的取り組みとして、DeepMindの機械学習技術を採用してデータセンターの冷却電力を40%削減する成果を上げている29。このシステムでは、データセンター内に数千個のセンサーを設置し、各設備の温度、消費電力、ポンプの速度、各種設定データを蓄積している29。
AI最適化の仕組みとして、ニューラルネットワークがこれらの稼働データと冷却設備の消費電力との間のパターンを学習し、データセンター内外の環境に合わせて冷却設備の運用を最適化する29。予測に基づいて冷却設備の運用を細かく調整することで、冷却設備の消費電力を最大40%削減している29。
5.2 予測制御技術
気候予測との統合として、ニューラルネットワークにデータセンター周辺の気温と気圧の時系列データを学習させることで、1時間後のデータセンター周辺の気候を予測可能になっている29。
Metaの強化学習アプローチでは、冷却システムの最適化に強化学習を適用し、様々な天候下で冷気供給を改善している30。パイロット地域の一つでは、供給ファンのエネルギー消費を20%削減、水の使用量を4%削減という成果を実証している30。
制御システムの高度化として、強化学習は制御システムを連続したシーケンシャルステータスとしてモデル化するため、データセンターの冷却に理想的である30。何千ものセンサーで収集したデータを分析することで、空気の流れの数値設定を微調整し、設定された動作パラメータから逸脱することなく最適な冷却効率を実現している30。
5.3 動的制御技術の発展
マツダの冷凍サイクル制御では、強化学習の報酬に冷媒の過冷却度とエバポレーターの放熱量を設定し、バッテリーの熱交換量を高く維持する制御システムを開発している31。これにより冷凍サイクルを安定制御させる上で必要となる膨張弁入口における過冷却度の確保を行っている31。
シミュレーター基盤の強化学習として、信頼性を確保するためシミュレーターに基づく強化学習アプローチが採用されている30。シミュレーターは物理学に基づくモデルを使用して、天候やIT負荷、その他の可変因子の変化に建物のシステムがどのような影響を受けるかを予測する30。
6. 高効率・高密度冷却システム
6.1 マイクロチャネル冷却技術
東京大学の革新的技術として、特殊な三次元マイクロ流路構造を持つ水冷システムが開発され、世界最高レベルの冷却効率と高い安定性を達成している27。このシステムでは、マイクロ流路に水を注入することで生じる圧力損失を従来の冷却方法と比べて62%減らしながら、1cm²あたり700W以上の放熱を実証している2。
技術的仕組みとして、2つのシリコン基板を組み合わせて作られ、一方の基板にはマイクロ流路が、もう一方には冷却水を効率よく分配するためのマニホールドが形成されている2。マイクロ流路の側壁付近に設置された微細な柱(マイクロピラー)がキャピラリー構造として機能し、毛細管現象により水の薄い膜が熱いシリコンに接触しやすくなる2。
性能指標として、冷却性能を表す「性能係数」が10万に達する世界最高レベルの冷却効率を達成している2。この技術により、AIチップや高出力電子機器の性能向上と省エネ化が可能となり、次世代電子機器の開発とカーボンニュートラルの実現への貢献が期待される2。
6.2 組み込み型ヒートパイプ技術
ヒートパイプの原理として、蒸発と凝縮の原理に基づいて熱を輸送する受動的二相熱伝達デバイスがある32。ヒートパイプは少量の作動流体で満たされた密閉された中空チューブで構成され、一端に熱を加えると作動流体が蒸発し、もう一方の端で凝縮して液体に戻る32。
設計方式として、一般的にヒートパイプ・ヒートシンクを使った放熱・冷却ソリューションには、フィン挿し型デザインとヒートパイプ埋め込み型デザインの2つの方式がある33。ヒートパイプは最小限の温度勾配で長距離にわたって効率的に熱を輸送するため、高温の電子コンポーネントから離れたヒートシンクに熱を伝達する際に非常に効果的である32。
実用応用として、ラップトップ、ゲーミングラップトップ、その他の小型デバイスで冷却性能を高めるために一般的に使用されている32。
6.3 モジュラー冷却システム
高密度対応技術として、液浸冷却により「間引き搭載」ではなくサーバやストレージを高密度に収める「フル搭載」が可能になっている12。富士通の液浸槽は19インチラックに準拠しており、16U分の容量でサーバなら128台、ストレージなら32台のスペースを提供する12。
スペース効率化として、槽は2段まで積み上げが可能で、空調用設備用のスペースが丸ごと不要になるため、データセンター全体では70%のスペース削減が見込める12。液体で機器を冷却すれば騒音問題も解決され、空冷と比べて40%の電力削減が可能である12。
CDU(クーラント分配ユニット)技術として、企業の電子機器やハイパースケール、IoT、クラウドシステムを正確に冷却して保護するシステムが提供されている34。CDUは、よりコンパクトで柔軟なソリューションでより高いレベルの冷却能力を提供し、データセンターコンポーネントの冷却と保護のための効率的なオプションとなっている34。
7. サステナビリティと環境配慮
7.1 省エネルギー技術
液体冷却による省エネ効果として、従来の空冷システムと比較して冷却コストを大幅に削減できる35。空冷方式では大量のファンを稼働させる必要があり多くの電力を消費するが、液体冷却ではファンや空調システムが不要になり、冷却に必要なエネルギー消費を大幅に抑えられる35。
具体的な削減効果として、富士通の液浸冷却技術では空気を冷やすことで機器を冷却する空冷式に比べて約1000倍の熱輸送効率を持ち、結果的にデータセンターの消費電力を40%節約することが可能である12。データセンターの冷却エネルギーを90%以上削減できる二相式液浸冷却システムも開発されている27。
AI最適化による省エネとして、Googleの事例ではDeepMindの機械学習技術により冷却設備の消費電力を40%削減し、PUE(電力使用効率)では15%の改善を達成している29。
7.2 低環境負荷技術
自然冷媒の活用として、マエカワは「ナチュラルファイブ」と呼ぶ方針で、アンモニア(NH3)、二酸化炭素(CO2)、水(H2O)、炭化水素(HC)、空気(Air)の5種の自然冷媒を利用している36。これらの自然冷媒は200℃から-100℃の温度域で加熱、乾燥、給湯、空調、冷蔵、冷凍と広く利用されている36。
NH3/CO2冷却システムは、地球温暖化に配慮した冷却ユニットとして開発された高効率冷却システムで、自然冷媒のアンモニアとCO2を組み合わせることでアンモニア漏洩リスクを抑え、CO2消費量・排出量を削減する36。
Opteon™ 2P50流体の特徴として、オゾン破壊係数(ODP)はゼロで、地球温暖化係数(GWP)は10.8と非常に低く、漏洩の可能性も限定的(年間1%未満)であるため、排出量が非常に少ない27。
7.3 リサイクル性と持続可能設計
放射冷却技術として、大阪ガスが開発したSPACECOOL®は、熱を-270℃の宇宙空間に逃すことにより、直射日光下でエネルギーを用いずに周囲より温度が低下する新素材である37。10年以上のUV耐候性があり、変色やスペクトル変化がないことが確認されている37。
環境適応型材料として、千葉大学などが開発した光ると冷える物質は、光を放出して物質の温度を下げるため、宇宙空間などの熱が伝わらない真空中でも温度を下げることができ、新たな需要が期待されている38。
循環型システム設計として、液浸冷却システムでは、熱交換装置で冷却された冷媒がタンクに戻りサーバーを再び冷却する自然循環型の仕組みが採用されている35。これにより、外部エネルギー投入を最小化した持続可能な冷却システムの実現が可能である。
8. 応用分野別の冷却要件と技術選択
8.1 データセンター冷却
高密度化への対応として、生成AIやビッグデータ、IoTなどの急速な発展に伴い、データセンターに求められる処理能力が大幅に増大し、高性能なサーバが多数設置されるようになっている35。AIサーバーにおける発熱密度は将来100W/cm²を超える勢いで3、従来の空冷方式では十分な冷却機能を果たせない状況になっている35。
液浸冷却の導入効果として、富士通の液浸冷却技術では空冷と比べて40%の電力削減、設置スペースの70%削減、騒音問題の解決を実現している12。KDDIは2020年に台湾で実証実験を実施し、基礎技術と冷却効果を検証して良好な結果を得ている39。
具体的なシステム構成として、液浸槽は19インチラックに準拠し16U分の容量があり、サーバなら128台(1Uの2CPUサーバを約3ラック分)、ストレージなら32台(4Uのストレージを約3ラック分)を収容可能である12。
8.2 IoTデバイス冷却
エッジコンピューティングの課題として、IoTの進展に伴いより分散化されたエッジ環境でのデータ処理ニーズが高まる中、省スペースかつ高効率な冷却技術が求められている40。旭化成ネットワークスは液浸コンテナ・データセンターの実証検証を行い、エッジ型データセンターソリューションの開発を進めている40。
小型化対応技術として、コンテナ型による設置の容易性・柔軟性、遠隔監視・運用管理の効率性、環境負荷低減効果を検証している40。液浸冷却による消費電力の削減効果や従来の空冷方式との冷却性能比較、高密度実装における冷却効果の評価が行われている40。
8.3 車載システム冷却
電気自動車への適用として、xEV(電動車)に搭載されるインバータでは、航続距離の伸長や燃費・電費向上のため、高出力化や小型化、軽量化が進んでいる41。パワーモジュールは走行時に高温となるため適切な冷却が欠かせない41。
冷却器の技術開発として、レゾナックはアルミの材料、成形加工、接合の技術を基盤に、設計と解析の技術を組み合わせ、顧客の仕様に合った冷却器を提案している41。Cu/Al複合材ベースにAlフィンの配列を狭ピッチ化するとCuヒートシンク相当の熱抵抗が可能で、重量はCuヒートシンク比で3分の1~半分程度に軽量化できる41。
車載冷却の特殊要件として、富士通は自動運転用高速プロセッサへの液浸冷却技術の転用を検討している42。エンジンルームは非常に高温で振動も大きいが、液浸冷却技術を適用することで様々なメリットが生まれると期待されている42。
8.4 医療機器冷却
高精度要件として、医療機器では機器の正確性と信頼性が患者の安全に直結するため、温度管理は極めて重要である。フェーズチェンジマテリアルは医療用途での温度管理に利用されており22、精密な温度制御が要求される医療機器の冷却に適用されている。
清浄性要件として、医療機器の冷却では汚染防止が重要で、液浸冷却技術では周りの空気環境がいかに汚染されていても影響を受けることがないため、医療機器への応用可能性がある42。
8.5 宇宙機器冷却
極限環境対応として、OKIは宇宙向けの電子部品を冷却する技術を開発している43。銅を使って熱を部品の外に排出する仕組みで、空気がないため冷却ファンによって風が生じない宇宙空間でも放熱性能を55倍向上させる43。
宇宙用クライオスタットとして、住友重機械工業は真空容器、液体ヘリウム容器、冷凍機を組み合わせた宇宙極低温システムを開発している4445。宇宙空間で微弱な光を高感度に捉えるため、センサーを冷却することが有効で、数々の人工衛星・探査機に極低温機器を供給している45。
具体的な宇宙機器応用として、赤外線天文衛星あかり、X線天文衛星ひとみ、月探査機かぐや、金星探査機あかつき、気候変動観測衛星しきさいなどに搭載されている44。冷却温度1.2K、冷却方式は超流動ヘリウム+4K冷凍機+20Kスターリング冷凍機、寿命3年以上の性能を実現している44。
9. 今後10年の技術ロードマップと課題
9.1 技術進化の予測
2025-2030年の発展予測として、IDTechExは二相式液冷を採用するにあたって生じる技術・商業両面における優位性と障壁について予測している46。単相式冷却はシンプルで定着しているもののメンテナンス面や技術面でのリスクが高く、二相式冷却は効率に優れるが環境に対する懸念があり初期コストも高い46。
冷凍空調技術ロードマップ2050では、2050年ビジョンとしてカーボンニュートラルな時代への貢献を掲げている47。2025年までに数kW級高信頼・高効率冷却システムの確立、2030年までに小型化(現状比1/10以下)及び高効率化を実現した冷却システムの確立が目標とされている48。
エネルギー・環境イノベーション戦略では、冷凍機、冷媒ポンプ、配管等を含むシステムとしての小型化、長尺化(km級)大容量化(1.5kV、10kA級)ケーブルの仕様決定、システムの低コスト化が2030年の目標として設定されている48。
9.2 商業化への障壁
初期投資コストの課題として、液体冷却システムは従来の空冷システムと比較して初期導入コストが高くなる傾向がある49。冷却液の種類、配管、熱交換器など新たな設備投資が必要である49。
技術的課題として、液体漏洩のリスクや冷却液の定期的な交換、配管のメンテナンスなど新たな管理体制の構築が求められる49。既存のサーバーラックやインフラストラクチャとの互換性が課題となる場合がある49。
人材・スキルの課題として、液浸冷却システムに携わるのは約20名で、技術開発や設計を推進するチームだけでなく、ビジネス化を推進するチームの組成が重要である42。新しい技術の習得と運用ノウハウの蓄積が商業化の鍵となる。
9.3 標準化とコスト課題
業界標準化の必要性として、液体冷却に関する業界標準がまだ確立されていないため、異なるベンダー間の互換性や運用ノウハウの共有が十分ではない49。一般社団法人日本液浸コンソーシアムが設立され、ステイクホルダーとの共創により国際競争力を強化し、世界に先駆けて標準化を進める取り組みが開始されている28。
コスト削減の方向性として、標準化によるコスト削減が期待されており、液浸コンテナ・データセンターの設計や運用が標準化されることで、製造コストや運用コストの削減が可能になる40。データセンターの物理的な設置面積の60%削減を実現し、設備投資(CAPEX)も最大33%削減できる可能性がある27。
規制・環境要件として、エネルギー効率指令(EED)、データセンター向け欧州行動規範(EU DC CoC)、ASHRAE規準、ISO 50001エネルギー管理システム、シンガポールのグリーンデータセンター標準などにより、データセンター運営者はエネルギーや水の使用、二酸化炭素排出量の規制圧力を受けている13。
10. まとめと将来展望
10.1 今後の研究開発の方向性
基礎技術の深化として、山口東京理科大学の結城和久教授らが開発した「ブリージング現象」を利用した二相液浸冷却技術は、人の呼吸現象を応用した自発的な液供給機能により世界最高の735W/cm²の冷却性能を達成している283。この技術は従来の実装可能な二相液浸技術の最大性能300W/cm²を大幅に上回る画期的な成果である。
材料科学の進展として、グラフェン、カーボンナノチューブ、合成ダイヤモンドなどの高熱伝導材料の実用化研究が加速している152021。特に合成ダイヤモンドは銅の5倍以上の熱伝導率(2000W/mK以上)を持ち、電気絶縁性も兼ね備えるため、次世代冷却システムの核心材料として期待される2021。
AI統合システムの発展として、GoogleやMetaが先導するAI・機械学習による冷却最適化技術は、冷却エネルギーの40%削減という実績を示している2930。今後は予測制御の精度向上と自律的な最適化システムの構築が重要な研究方向となる。
10.2 産業界・学術界への提言
産業界への提言として、第一に、データセンター事業者は従来の空冷システムから液体冷却システムへの移行を積極的に検討すべきである。特にAIワークロードの増加により発熱密度が急激に上昇する中、将来を見据えた冷却インフラの整備が競争力の源泉となる。
第二に、半導体メーカーと冷却システムメーカーの連携強化が不可欠である。チップ設計段階から冷却要件を考慮した統合設計アプローチにより、システム全体の効率化を図るべきである24。
第三に、標準化への積極参加が重要である。日本液浸コンソーシアムのような業界団体を通じて、国際標準の策定に主導的な役割を果たし、日本の技術優位性を確保する必要がある28。
学術界への提言として、第一に、基礎研究と実用化研究の架橋を強化すべきである。山口東京理科大学のように産学連携により基礎研究成果を実用化まで発展させる取り組みが模範となる283。
第二に、学際的研究の推進が必要である。熱工学、材料科学、AI・機械学習、流体力学など複数分野の融合により、革新的な冷却技術の創出を目指すべきである。
第三に、人材育成の強化が急務である。次世代冷却技術に関する専門知識を持つ人材の育成を通じて、産業界のニーズに応える研究開発体制を構築する必要がある。
10.3 社会実装に向けた課題と展望
技術的課題の解決として、液体冷却システムの信頼性向上とメンテナンス性の改善が重要である。特に液体漏洩のリスク軽減、システムの長寿命化、予防保全技術の開発が求められる49。
経済性の改善として、初期投資コストの低減と運用コストの最適化が社会実装の鍵となる。標準化による量産効果、モジュラー設計による設計・製造コストの削減、AI最適化による運用効率の向上を通じて、経済的優位性を確立する必要がある2740。
環境・社会的価値の創出として、冷却システムの省エネ化はカーボンニュートラル社会の実現に直結する重要な技術である。特にデータセンターの冷却エネルギー消費が2030年までに900TWhに達する予測の中13、革新的冷却技術の普及は地球環境保護に大きく貢献する。
グローバル展開の戦略として、日本の技術優位性を活かした国際展開が重要である。特にアジア太平洋地域でのデータセンター需要増加を捉え、日本発の冷却技術を世界標準として確立することが期待される42。
将来の技術融合として、冷却技術と他の革新技術との融合により、新たな価値創造が可能である。例えば、廃熱回収技術との組み合わせによるエネルギーの循環利用、IoT・5G技術との統合による遠隔監視・制御システムの高度化、量子コンピューティングとの融合による極低温冷却技術の発展などが展望される。
冷却システムの未来は、単なる熱管理技術を超えて、持続可能な社会の実現を支える基盤技術として位置づけられる。産学官の連携により、技術開発から社会実装まで一体的に推進することで、日本が世界の冷却技術をリードし、地球環境と経済発展の両立を実現することが期待される。
- http://www.jstage.jst.go.jp/article/jiep1998/4/5/4_5_398/_article/-char/ja/
- https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2025-04-14-001
- https://www.socu.ac.jp/news/2025/06/post-869.html
- https://note.com/nekonyannko222/n/neb73342fdc4d
- https://enterprisezine.jp/news/detail/21957
- https://www.tongyucooler.com/ja/news/ai-server-cooling-challenges-a-battle-between-temperature-and-performance/
- https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/news/4747
- http://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaib/77/774/77_774_395/_article/-char/ja/
- https://ja.sindathermal.com/info/liquid-cooling-vs-air-cooling-101923940.html
- https://burrtec.co.jp/datacenter/useful_content/air_cooling-water_cooling/
- https://jpn.nec.com/rd/technologies/datacenter_cooling/index.html
- https://kn.itmedia.co.jp/kn/articles/1705/25/news158_2.html
- https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2411/25/news067.html
- https://sasutena-mirai.com/noise-from-grid-batteries-problem/
- https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/2534425/eng2894.pdf
- https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_graphene-and-carbon-nanotubes/
- https://www.daigasgroup.com/rd/topic/1310107_53539.html
- https://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama/papers/05/thermophys.pdf
- https://www.semanticscholar.org/paper/c1f18a0f8283c2bc7ab0f64a28831f7de56ba9a7
- https://www.semiconportal.com/archive/editorial/technology/process/130830-elementsix.html
- https://www.coherent.com/ja/news/blog/diamond-heat-spreaders
- https://scrapbox.io/sustainable-living-lab/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%9E%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88PCM%EF%BC%89
- https://www.shinetsusilicone-global.com/catalog/pdf/PCM.pdf
- https://www.silicone.jp/products/notice/125/index.shtml
- https://www.tongyucooler.com/ja/news/immersion-cooling-technology-the-future-of-data-center-heat-management/
- https://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/141.html
- https://www.opteon.com/ja/applications/two-phase-immersion-cooling
- https://mainichi.jp/articles/20250603/pr2/00m/020/488000c
- https://xtech.nikkei.com/it/atcl/news/16/072102162/
- https://www.infoq.com/jp/news/2024/12/data-center-sustainability-ai/
- https://www.mazda.com/content/dam/mazda/corporate/mazda-com/en/pdf/innovation/monozukuri/technology/tech-review/2025/2025_no001.pdf
- https://www.winmate.jp/ja-JP/Blog/blog-heatsink-cooling-explained
- https://www.furukawa.co.jp/product/catalogue/pdf/thermal.pdf
- https://jp.boydcorp.com/blog/designing-data-center-coolant-distribution-units-cdu.html
- https://www.sbbit.jp/article/cont1/159638
- https://www.smri.asia/jp/mayekawa/news/7075
- https://www.daigasgroup.com/rd/topic/1310161_53539.html
- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOSG032TE0T00C24A9000000/
- https://journal.meti.go.jp/p/39339/
- https://www.aknws.com/news/250523/
- https://www.resonac.com/jp/solution/alcu-heatsink.html
- https://www.fujitsu.com/downloads/blog/jp/journal/2019-04-26-02.pdf
- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC069U00W4A201C2000000/
- https://www.shi.co.jp/industrial/jp/product/science/space/cryostat.html
- https://www.shi.co.jp/industrial/jp/product/science/space/
- https://www.idtechex.com/ja/research-article/20108-30456-24335-28082-20919-12495-12452-12456-12531-12489-gpu-12398-26410-26469/31999
- https://www.jsrae.or.jp/jsraeRM/RMdigest.pdf
- https://www8.cao.go.jp/cstp/nesti/suishin/nestiroadmap.pdf
- https://note.com/kishioka/n/n248d12d49ded
- https://www.semanticscholar.org/paper/b648b33355f3c8a0244ae035bae9773ae7342299
- https://www.semanticscholar.org/paper/bfe5a622e9494a8c93b7a5a5dda667328fea087f
- https://www.semanticscholar.org/paper/ee39f07eb9065dff54d07406d2bfe343582cb00b
- https://www.semanticscholar.org/paper/65ed9c2d3fa16ed6432a24189769f12bd8754cf8
- https://www.semanticscholar.org/paper/1e25191fde9cb4ddca2c35a7ae0a81bd17880e44
- https://www.semanticscholar.org/paper/351b1898d20a28f8e935c0c52f1c8904430af8e9
- https://www.klv.co.jp/corner/power-semiconductor-cooling.html
- https://www.science-t.com/book/M069.html
- https://www.mirait-one.com/miraiz/whatsnew/trend-data_0031.html
- https://www.semanticscholar.org/paper/9e16f8970188594597cb3c83fbb0488eaede1b32
- https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/2021-03/210324_shimakawa-0f3925f7c287ec499de9368727b1feec.pdf
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/reajshinrai/29/7/29_KJ00004740921/_article/-char/ja/
- https://www.semanticscholar.org/paper/ff928bd054374c91df942c67d73d8d9afa3e3887
- https://www.semanticscholar.org/paper/6a15e027fde437030d85411587465c0ca93706c9
- https://www.semanticscholar.org/paper/13d12ce9655cc19375abad4bdffa3f5f941277e3
- https://www.semanticscholar.org/paper/9865c66f67dc7de4677f30f7b6f09003a66d4fc5
- https://www.semanticscholar.org/paper/b393667c2463e80cd50f634c9853a3e5aa3e3e66
- https://www.arrozcorp.com/archives/column/019
- https://www.semanticscholar.org/paper/46e5f977171c1fd016e02d196acb9fa6a63a8f9a
- https://www.semanticscholar.org/paper/b8d8d1fd106350bf99b6f5f98c3032e2bc9eb7cc
- https://www.semanticscholar.org/paper/377000e719a4d8a9607cb3200807d304dd3d532b
- https://www.semanticscholar.org/paper/a3c5ed31dec4957a522124d079f67fc3916af909
- https://www.semanticscholar.org/paper/32f97f98656992833af1aff4722ddf352d8fdb2b
- https://www.mdpi.com/2072-666X/13/9/1420
- https://www.t.u-tokyo.ac.jp/hubfs/press-release/2025/0414/001/text.pdf
- http://alba.ifs.tohoku.ac.jp/IFS_WE/japanese.html
- https://www.semanticscholar.org/paper/582a8aecf89e789f73362ba4e7acbf269aa45f7a
- https://www.semanticscholar.org/paper/1755e88ca019f2ab5a0790471d287dd82688e929
- https://www.semanticscholar.org/paper/95c2429372597ebe95fb6c25bb653877652f8e16
- https://www.semanticscholar.org/paper/8770a8f7406b0fff0784faa153f8b6e1ad9a9fdb
- https://www.adb.org/sites/default/files/publication/877951/adbi-wp1374.pdf
- https://www.mdpi.com/2673-4931/18/1/17/pdf?version=1662717238
- https://www.env.go.jp/earth/2024kenshouhyouka/R6_3datufuron.pdf
- https://www.jll.com/ja-jp/insights/what-is-a-green-data-center-that-utilizes-liquid-cooling
- https://www.joneslanglasalle.co.jp/ja/trends-and-insights/cities/what-is-a-green-data-center-that-utilizes-liquid-cooling
- https://www.semanticscholar.org/paper/a721019f4d2befe9c24ff45bfb7a074f6959ae60
- https://www.semanticscholar.org/paper/0cc9f7546e5a118fe3c219da3ee4896dde056f2f
- https://www.jsme.or.jp/technology-road-map/uploads/sites/16/2024/04/20240321seminar_1.pdf
- https://www.idtechex.com/ja/research-article/12302-12487-12540-12479-12475-12531-12479-12540-12398-28082-20307-20919-21364-12303-idtechex-webinar/31864
- https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/kosokuro_kaihatsu/pdf/005_01_00.pdf
- https://www.semanticscholar.org/paper/2f44a17b0e91362828923cc93c7b6dd8527c19ef
- https://www.semanticscholar.org/paper/66c8f6f6fdaf1676c8b6fc6b9e016b7bf06a5c28
- https://www.semanticscholar.org/paper/cf9ffdeca1cc257e712e9fb9bc91156411a22048
- https://www.semanticscholar.org/paper/d6ab470930e7c1e5827f49185cb3641a0c68c5fd
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/58/4/58_286/_article/-char/ja/
- https://www.semanticscholar.org/paper/3cf08a23d861201faf8cfd67f314355600e17ea6
- https://spacecool.jp/news/20250530/
- https://www.tmu.ac.jp/news/topics/34973.html
- https://www.jaea.go.jp/about_JAEA/business_plan/2022j-parc-sochi.pdf
- https://www.idaj.co.jp/blog/solution/electronics-thermal-management/thermal-design-210927
- https://www.semanticscholar.org/paper/9f2c925ac91f90c92fd99bbb6f8b6f2624160428
- https://www.semanticscholar.org/paper/9ef3d8d97a588560d7331528da9bd70f81f98313
- https://www.semanticscholar.org/paper/351649060da063b3ed04cb73e5965e5710a27153
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejfms1990/115/12/115_12_1271/_article/-char/ja/
- https://www.semanticscholar.org/paper/8553d6c080a813ab9a4a146ce51c869b31b4a561
- https://www.semanticscholar.org/paper/a953cc67ecadf735660fe3b8ab4293046eb90ca6
- https://www.semanticscholar.org/paper/081233ae6a29102d6e2907dea62e7079e290beb9
- https://www.semanticscholar.org/paper/302cdd1d264b9a6efa7f8e77dd54797ebef1aee3
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9503348/
- https://res.mdpi.com/d_attachment/micromachines/micromachines-09-00287/article_deploy/micromachines-09-00287.pdf
- https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fther.2024.1345452/pdf?isPublishedV2=False
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4665581/
- https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17686015
- https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/nanoph-2023-0627/pdf
- https://academic.oup.com/nsr/advance-article-pdf/doi/10.1093/nsr/nwac208/46212787/nwac208.pdf
- https://www.mdpi.com/2076-3417/14/1/195/pdf?version=1703577559
- https://www.mdpi.com/2305-6703/4/3/7
- https://jpn.nec.com/ad/onlinetv/space202212-2.html
- https://www.semanticscholar.org/paper/e5b749fce3c7dc4f26150a8874d4eb34a2b33c8a
- https://www.semanticscholar.org/paper/9f47487e5f7c71c46323e6f8358f81e36cd7b1ee
- https://www.semanticscholar.org/paper/ae80869f95805503d278ae1e4a4858d3160b6ed3
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/spm/2004.Spring/0/2004.Spring_242/_article/-char/ja/
※本ページは、AIの活用や研究に関連する原理・機器・デバイスについて学ぶために、個人的に整理・記述しているものです。内容には誤りや見落としが含まれている可能性もありますので、もしお気づきの点やご助言等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
※本ページの内容は、個人的な学習および情報整理を目的として提供しているものであり、その正確性、完全性、有用性等についていかなる保証も行いません。本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことによって発生した損害(直接的・間接的・特別・偶発的・結果的損害を含みますが、これらに限りません)について、当方は一切責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の責任でお願いいたします。